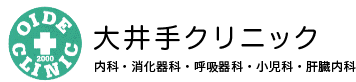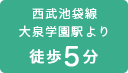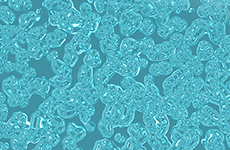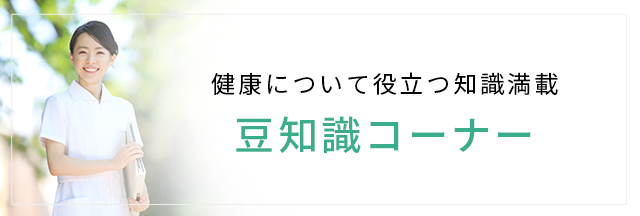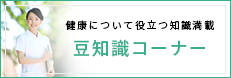2001年12月1日
生活習慣病 その3
高血圧

今月は高血圧についてです。どうして血圧が上がるのか?若くして高血圧になってしまった場合には褐色細胞腫などのカテコラミン産生腫瘍、腎動脈狭窄によるレニン・アンギオテンシン系の活性化、副腎腫瘍による高アルドステロン症、甲状腺機能亢進症などなど、ホルモン異常が関与している可能性を考えなければなりませんが、加齢と伴に上昇する血圧の場合は、動脈硬化を主因とします。では、なぜ動脈硬化が起こるのか?加齢と伴に血管壁のエラスチンが減少して弾力性が低下し、50才を過ぎる頃から血管壁の硬化が進行します。また、高コレステロール血症ではマクロファージにコレステロールが貪食されて血管壁にこびりついて血管壁の内腔が狭小化すると伴に硬くなっていきます。その他に、塩分の摂りすぎや運動不足での発汗低下がナトリウム貯留を招いたり、体重の増加が心機能に負担をかけて血圧が上がります。最近、早朝高血圧が話題になっています。
これは、家庭血圧計や24時間自由行動下血圧測定法が普及したため、病院以外での血圧が注目され、特に新血管系のイベントが多い早朝血圧に関心が集まりました。覚醒時には急激に交感神経系が賦活化されたり、レニン・アンギオテンシン系が早朝4時頃から覚醒時をピークに活性化されるため、朝が一番血圧が上昇しやすいのです。生活習慣病として高血圧を考える場合には、やはり肥満、運動不足、高脂血症、塩分の過剰摂取が主要因ですので、それらを日常生活のうえで是正していけば、予防と治療になります。
高血圧の治療
まずは高血圧を助長している生活習慣を見直し、先月号でご紹介したBorg指数から適度な運動量を決定して、無理なく継続することです。高血圧家系の方も最初から薬に頼ることなく、まず運動や食事療法から始めます。ただし、少し歩くとすぐ膝が痛くなる方は(加齢による変形性膝関節症)、運動する前に、まず膝を包んでいる筋肉を鍛えて膝関節を保護しなければなりませんので、太ももの筋肉を鍛える必要があります。
我が国の高血圧治療ガイドラインで第一選択薬とされている薬物には利尿剤、カルシウム拮抗剤、α遮断薬、β遮断薬、アンギオテンシン変換酵素阻害剤、アンギオテンシンⅡ受容体拮抗剤があります。それぞれには、利点と副作用があるため、個々のケースに応じてどれから使用していくか検討します。最近は腎臓をはじめとした臓器保護作用のあるアンギオテンシン変換酵素阻害剤が多用されるようになり、次のアンギオテンシンⅡ受容体拮抗剤にもその期待が寄せられています。