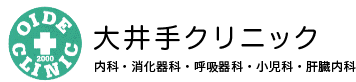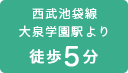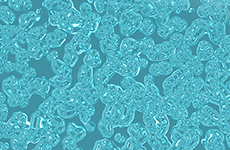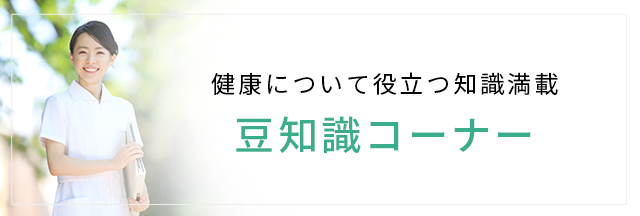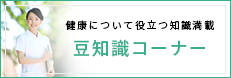2002年10月1日
胃・十二指腸病変
ヘリコバクターピロリ菌 (その3)

今月はピロリ菌の最後です。アメリカ国立衛生研究所が1994年4月に「ピロリ菌陽性の消化性潰瘍に対しては初発再発を問わず除菌療法を行うべき」と勧告し、日本ではその6年後の2000年11月にようやく保険適用となりました。先月紹介した低悪性度胃MALTリンパ腫に関しては専門施設で除菌を行うこととしました。次に除菌が考慮されるべき疾患としてあげられるのが胃癌です。現在「除菌により胃癌を予防出来るのか?」という点が最大の課題となっています。除菌療法が保険適用される前にピロリ菌陽性者と陰性者を10年間追跡調査したある施設の結果では、ピロリ菌陽性者からは2.9%の胃癌発生を認めたましたが陰性者からは認めなかったとのことです。また、スナネズミを使った動物実験でも、ピロリ菌と発癌物質の組み合わせで胃癌を発生させることができるので、ピロリ菌と胃癌の因果関係はありそうです。しかしながら、日本人のピロリ菌感染率は40才以上では70%以上に及びますがその全員に胃癌が発生するわけではないので、発癌のメカニズムにはピロリ菌感染の他にピロリ菌の種類や産生する毒素、遺伝子変異、その他多くの因子が関与しているはずです。やはり注目すべき点は「ピロリ菌の除菌療法で胃癌が予防出来るか否か」でしょう。たとえ高齢者の方でもピロリ菌陽性と診断された時点で除菌すれば胃癌発生から逃れられるのか? ピロリ菌感染による非萎縮性胃炎の段階では除菌により胃炎の治癒が可能となっています。しかしながら年余にわたってできあがってしまった萎縮性胃炎や腸上皮化生まで進展した胃炎は除菌で治癒可能か否かは結論がでていません。(下段に続く)
ピロリ菌の感染診断と除菌判定
胃癌の背景にはこれらの強い胃炎が存在しているため重要な問題です。我が国では国立がんセンターを中心にして除菌しない人のボランティアを集めて胃癌の発生率を検討しようとしましたが、やはり胃癌ができるかもしれないという状況下でのボランティアは集まるわけがなく、この計画は頓挫しました。一方、早期胃癌を内視鏡で切除して治療する手技(EMR)が定着してきましたが、EMR後に除菌をすると、しなかった場合よりも胃癌の再発率が有意に抑制されることが判明しており、除菌療法が胃癌発生を抑制することが強く示唆されています。 しかしながら、除菌後にも胃癌発生の報告があることから、発癌のメカニズムは単純なものではないことが伺えます。除菌後の問題点としては酸分泌能が回復することで胃酸が増え、食道に逆流して食道炎を起こして胸焼けなどの逆流性食道炎が20%前後の人に発生することです。また、胃の調子が良くなるために過食による体重増加も指摘されています。